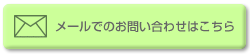腎臓は2つあり、次の作用をします。
血液の中の老廃物を尿にしたり、必要な水分を再び体に吸収したり
また血液を作るためのホルモンを出したり、血圧をコントロールするホルモンも出します。
体にとってはもちろんとても大切な臓器の一つです。
ところがこの腎臓はとことん異常が起こらないと症状を出しません。これがとても厄介なのです。
例えば血液検査で尿素窒素(BUN)やクレアチニン(CRE)を測定するのですが、これらに異常が出た時にはすでに75%が壊れているのです。
言葉を換えれば25%以下しか正常な細胞が残っていないという事です。
この段階でもある程度の生活レベルは守れますが、もちろんもっと早期に診断ができるとさら良いに違いありません。
そこで積極的に尿検査を実施します。
尿中の蛋白、潜んでいる血液(潜血)、酸性・アルカリ性の傾き(pH)、尿の重さ(尿比重)を主に測定します。
特に尿比重は重要で、尿が作られるときに通過してくる尿細管の機能がある程度わかるのです。尿細管で尿中の水分を吸収したりする能力が低下すると、尿がとても薄くなり量も多くなります。いわゆる尿細管の透過性が高まると言い、腎不全の兆候の一つに数え上げられます。
しかし塩辛いものを食べたあとお水をたくさん飲むと尿は薄くなりますし、たくさん運動して飲み水をあまり飲んでないと濃くなったりしますから、たった1回の尿検査で薄いからと言って異常と決めつけられるものでもありません。数回検査した上で評価する必要があります。
また最近血液検査で15kg以下の犬ではシスタチンCという物質を測定することで、腎臓のろ過機能を判断することができる方法も取り入れられてきております。(シスタチンCとはタンパク質の一つで、腎臓の糸球体で濾過されたシスタチンCが尿細管で再度吸収されることがわかったため、尿細管の再吸収能力を見ることが出来るわけです。)
クレアチニンは痩せている個体は少ない値が出ますが、シスタチンCはそのようなことがありません。
その他ナトリウムやクロールも尿細管で再吸収される物質ですので、病気の段階により高く出ることも低く出ることもあります。
7歳を過ぎたころ
尿の量が多いなあ。薄いなあ。飲み水の量も多いなあと感じたとき
は血液検査と尿検査を受けてください。
早期なら食事管理がとっても有効です。(腎臓を治す薬はありません。)