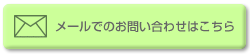検査機器は動物病院にとってはなくてはならない周辺機器です。
これがどうも連休とかお盆とか正月など、メンテナンスが効き難いときに作動がおかしくなったり壊れたりします。
昨日も血液検査のために遠心分離を始めて数秒後、大きな音がバリバリバリバンバンバン!!
以前にもこれは経験した音です。小型の遠心分離機ですが、高速回転で回っているため、相当なGがかかっています。ですから毎回バランスをしっかりと調整してスイッチを入れています。
が、ローターという部品が経年劣化するので交換してやるのですが、この交換時期が判りづらく遅れてしまうと破壊されてしまうのです。
そう言えば先週も作動がおかしかったので、ゴム製のパーツを新しいのに付け替えたのですが、その時ローターを見ても異常に気付きませんでした。
たまたま新しいのがあったので、早速取り替えて難を逃れました。
そしてほぼ同時期にレントゲンの機械の不調も・・・。夜症例の検討をしようとスイッチを入れたところ、「ネットワークが見つかりません。」とコマンドが出ました。
連休に入るし困ったなあとメーカーのメンテナンスの緊急連絡先に助けを求めました。そして担当者から連絡が再度入ると約束が得られたので、もう一度機械のチェックを行ったところ、スイッチング・バブという機械のパワーランプがついていません。どうやらこれが作動していないからネットワークに繋がっていない可能性が出て来ました。
担当者と連絡が取れた際、このことを告げ、翌日電気量販店で機器を購入し新しいものに付け替えたところ、レントゲンの機械は作動してくれました。
まずは難を逃れたようです。これで作動しなければ担当の方に連休中にも関わらずご足労願うところでした。勿論高い出張料と共にです。
まだ連休の序盤。機械もそうですが、健康を壊してはいけません。十分にご注意ください。
それにしても何でだろうね。長期休暇中の故障・・・・・・・。機械の神様もお休みなのでしょうか。